睡眠時無呼吸症候群とお口の関係について
ご家族の方から、寝ている時に息が止まっていると言われたことはありませんか?
睡眠中に無呼吸を繰り返すことで、様々な合併症を起こす病気を「睡眠時無呼吸症候群」と呼んでいます。睡眠時無呼吸症候群は無呼吸が起こる原因によって呼吸中枢の働きが低下することによって起こる中枢型、閉塞型、混合型に分けられます。最も多いのがのど、気道が何らかの理由で圧迫されたり、塞がったりすることで無呼吸状態(10秒以上呼吸が止まること)と大きないびきを繰り返す閉塞型 です。
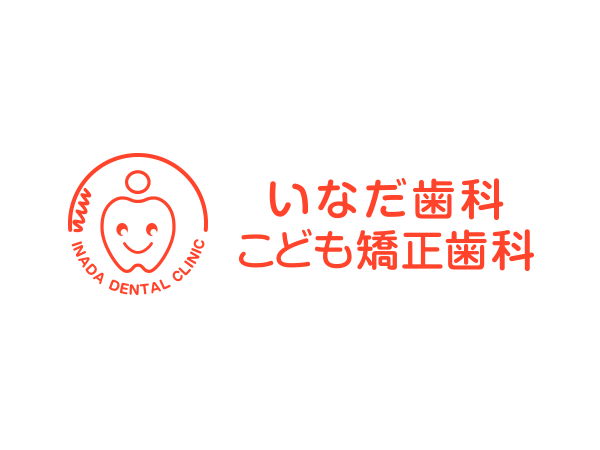
良質な睡眠が妨げられるため、日中強い眠気を感じたり、体力の回復不足や疲労感、集中力、記憶力の低下などの症状を引き起こします。無呼吸が続くと体内の取り込まれる酸素の量が不足し、心筋梗塞や脳卒中、糖尿病など様々な合併症を引き起こします。
主な原因は肥満による喉周りの脂肪ですが、顎が小さい、舌が大きい、扁桃が大きいといった生まれつきの身体的特徴や慢性的な鼻炎など耳鼻科領域の病気が原因となることもあります。
ところであごの形や歯並びも睡眠時無呼吸症候群の発症リスクに関係があるということをご存じですか?
欧米人と比較して日本人はもともとあごが小さく、気道が狭くなりやすい骨格的特徴を持っていて肥満でなくても睡眠時無呼吸症候群になりやすいと言われています。
発症リスクが高まるとされているお口の状態は
①顎が十分に発育しておらず、上あご・下あごが小さい
②下あごが後ろに位置している
③開咬(奥歯でかみしめても前歯がかみ合っていない状態)
④過蓋咬合(上の歯が下の歯を大きく覆っている状態)
⑤叢生(歯が重なり合って並んでいる)
⑥出っ歯や受け口
です。
あごが小さかったり歯並びが悪かったりすると、口の中のスペースが狭くなり舌が喉の奥に落ち込みやすくなったり、気道がふさがれやすくなります。
子供の重症のいびきや無呼吸では発育、発達にも影響が出ます。扁桃やアデノイドの肥大、アレルギー性鼻炎、蓄膿症などが原因となって引き起こされるケースが多いのですが、子どもの身体は、成長ホルモンが分泌されることで身長が伸びたり、体重が増えたりして、大人の身体つきへと成長していきます。成長ホルモンは、夜間深い眠りについているときに最も分泌量が増えるホルモンと言われており、睡眠時無呼吸症候群により眠りが妨げられることで、分泌が抑えられてしまいます。また、子供の歯並びやあごの発達は、将来的な気道の広さにも大きく影響します。
歯科で行う睡眠時無呼吸症候群の治療は
①睡眠中の気道を広げるためのマウスピース
軽度から中等度の方に対して睡眠時に下あごを前に出すことで、気道を広げるためのマウスピース型装置があります。歯科医院で睡眠時無呼吸症候群用のマウスピースを保険で作る場合、医科からの紹介状が必要となります。
②歯列矯正・顎矯正
根本的な改善が必要な場合、歯列矯正や顎矯正が検討されます。子供であれば拡大床や顎の発育を促す装置を用います。歯並びやあごの成長をみて必要に応じて矯正治療を早期に行うことで、将来的な睡眠時無呼吸症候群のリスクを下げることができます。口呼吸や扁桃肥大が疑われる場合は、小児科・耳鼻咽喉科・歯科の連携が必要となります。
口呼吸、肥満、アルコール摂取、喫煙などの生活習慣も睡眠時無呼吸症候群の発症に影響します。歯並びや顎の問題があっても、生活習慣の見直しや体重管理によって症状の緩和につながるケースも多々あります。また、意外に知られていない事として、ラグビーやアメフト、パワーリフティング、柔道など首を鍛える必要のあるスポーツなどをされていると、脂肪ではなく筋肉で気道が狭まり、睡眠時無呼吸症候群が起こることも分かってきています。治療を行うことで睡眠時の呼吸が改善され、身体のリカバリー力が高まるとスポーツ選手の間でも注目されてきています。
睡眠時のいびきや日中の眠気など気になる症状がある方はご相談ください。
