その症状、飲んでいるお薬が影響しているかもしれません
「最近、なんだか口の中が乾燥するようになってきた」
「毎日歯磨きをしているのに歯ぐきがぷっくりと腫れている」
「口内炎がひんぱんにできるようになった」
このような症状は飲んでいらっしゃるお薬が影響している可能性があります。
超高齢社会といわれる現在、複数のお薬を飲んでいらっしゃる方が増えています。飲んでいらっしゃるお薬によっては、お口の状態に影響したり、歯科治療後に痛みや腫れ、治りが悪くなったりすることがあるので注意が必要です。
病院や薬局に行かれる際には「お薬手帳」を持っていかれると思います。歯科でも「お薬手帳」を持っていく必要があるの?と思われるかもしれませんが、患者さんの持病や服用しているお薬について把握し、配慮することが安全に歯科治療を行ううえでとても重要なので是非お持ちください。治療を進めていくなかで患者様のかかりつけ医にご相談させていただくこともございます。
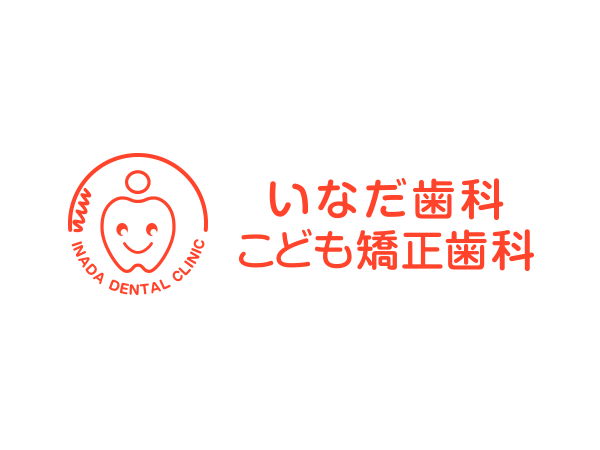
① 歯ぐきの腫れ
歯ぐきの腫れの原因として多いのは歯肉炎や歯周炎ですが、薬の副作用でも腫れることがあるのをご存じですか?
副作用として歯肉の腫れが報告されている代表的なお薬をご紹介します。
1.けいれんを止める抗てんかん薬のフェニトイン(商品名:アレビアチン、ヒダントールなど)
フェニトインが入った薬を長期服用した場合、副作用として50%以上の方に歯ぐきの腫れが
認められるという報告があります。
2.高血圧治療薬のうちカルシウム拮抗薬(商品名:ニフェジピン、アムロジンなど)
カルシウム拮抗薬を長期間服用している人で歯ぐきの腫れが認められる割合は約20%と
言われています。
3.臓器移植や自己免疫の病気で用いられる免疫抑制剤シクロスポリン
(商品名:サンディミュン、ネオラールなど)
軽度の場合は歯と歯の間の歯ぐきが少し腫れる程度ですが、重症化すると歯が隠れるほど歯茎が腫れることもあります。
重症化しやすい傾向としては
1.口腔内の清掃状態が悪い
2.年齢が若い
3.服用量が多い
です。
歯ぐきの腫れの予防には日々のブラッシングと歯科医院でのメインテナンスが重要です。歯石がついていると歯ぐきへの刺激となり歯ぐきの腫れがおこりやすくなります。歯科医院で定期的にメインテナンスを受けていただき歯石や磨き残しをチェックし、お口の中をきれいに保つことが大事です。歯が隠れるほど歯茎が腫れている場合、歯ぐきの腫れによって歯磨きが難しくなるという悪循環に陥るため、歯肉を切除する場合もあります。
② 歯ぐきからの出血
心筋梗塞や心房細動,脳卒中などの治療のため、血液をサラサラにするお薬(抗血栓薬・抗凝固薬)を飲まれている方も多くなってきています。
歯磨きや食事をしている際に歯ぐきから出血する場合、その原因の多くは歯肉炎や歯周炎ですが、血液をサラサラにするお薬を服用していて歯ぐきが傷つくと出血がなかなか止まらないことがあります。
また、歯科の治療で抜歯、インプラント、歯周外科治療、深い歯石の除去などの処置に関しては出血のコントロールに注意が必要です。歯科治療の時に出血が止まらないと困ると言ってご自身の判断で服用は止めないでください。
③ 口の中が乾燥する
口の中が乾燥する原因として薬の副作用以外にも年齢的なものやストレス、口呼吸などがあげられます。
唾液の分泌が低下して、お口が乾いた状態を引き起こす可能性のある薬剤は、
・抗アレルギー薬
・抗うつ薬
・抗不安薬
・抗パーキンソン病薬
・降圧薬
などがあげられます。
日本医薬品集に掲載されている薬剤全体の約1/4である700種類以上に口渇、口内乾燥、唾液分泌減少の副作用がみられるそうです。
軽度では口の中がネバネバしたり、ヒリヒリしたりします。プラークが歯の表面に付着しやすくなって口臭やむし歯の原因にもなります。重度になると、強い口臭、舌表面のひび割れ、痛くて食べ物が食べにくい、会話がしづらいなどの症状がでてきます。
治療としては、生活指導や対症療法が中心となります。唾液の分泌量が増えるように唾液腺マッサージをしたり、保湿性薬剤、保湿性の高い洗口液、保湿ジェル、スプレーなどを使用したり、こまめに水分補給をするように心がけることも有効な方法です。
④ 口内炎ができやすい
口内炎ができやすい服用薬の代表薬は抗がん剤です。
がん治療中は抗がん剤治療、放射線治療に伴う免疫力の低下によって、高い頻度で口内炎を発症します。
その他抗菌薬、解熱消炎鎮痛薬、降圧薬(Ca拮抗薬)、抗てんかん薬、免疫抑制薬などが原因でも口内炎を発症することがあります。
口内炎がいつまでも治らなかったり、急激に悪くなったりするような場合は、放置せずご相談ください。
より安全な歯科治療を行うためには持病やお薬の情報は欠かせません。歯科を受診される際にも「おくすり手帳」をご持参ください。
また、お薬に変更がある場合や新しい薬を追加処方された場合などはその都度お知らせください。

