再石灰化ってよく聞くけどどういうことなの?
「再石灰化」ってよく聞く言葉だけど、どういうことなの?と思われたことはありませんか?
歯の一番外側の組織、エナメル質は人間の体の中で最も硬い組織で、カルシウムとリン酸から成る ヒドロキシアパタイトの結晶からできています。水晶と同じくらいの硬さがあり、個人差はありますが2〜3㎜の厚さがあります。エナメル質の中にある象牙質や歯髄は、熱さや冷たさなどの刺激に敏感なので、それらの刺激から保護する役割を果たしています。虫歯によって穴が開いたり、食いしばりや歯ぎしりで欠けてしまうと自然には再生しません。
エナメル質は再生しないけど修復できることをご存じですか?
虫歯菌が出す酸や、食べ物や飲み物に含まれる酸によりエナメル質が溶けてしまう状態を「脱灰 」といいます。脱灰した歯は、フッ素を塗布することや唾液に含まれている成分が溶けた歯のエナメル質の中に戻ることで、歯のエナメル質が修復される作用がはたらきます。これを「再石灰化」といいます。軽度の脱灰であれば再石灰化で修復されるため、初期虫歯の段階であれば歯を削ることなく自然治癒ができます。「再石灰化」は、歯を脱灰から守る唾液の自然治癒メカニズムなのです。
口の中では、常に「脱灰」と「再石灰化」が繰り返されていて、再石灰化で再び結晶化させ修復することで歯の健康が守られています。2つのバランスが崩れて、脱灰に傾くとむし歯が進行します。
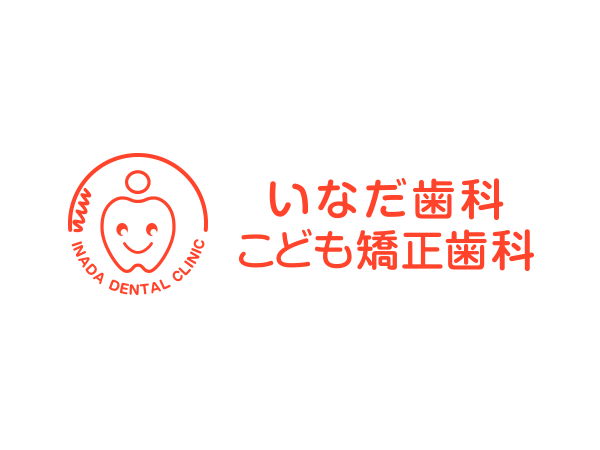
「再石灰化」を促すために私たちはどうすればよいのでしょうか?
①フッ素配合歯磨剤の使用や定期的に高濃度のフッ素塗布を受ける
毎日の歯磨きで使っている歯磨剤の多くには、再石灰化を促進する「フッ素」が含まれています。フッ素は再石灰化を促進させることができるほか、「酸に 強い歯質」を作り、むし歯菌の活動を抑えて酸を作らせなくすることもできます。毎日のケアでフッ素をしっかり取り入れ、定期的に歯科医院で高濃度のフッ素塗布を受けられることでむし歯予防効果が上がります。
②間食を控える
飲食の階数が多いと、それだけ細菌にえさとなる糖を与えてしまうので脱灰が起こりやすくなり、再石灰化の働きが追い付きません。口の中が酸性になっている時間が長くなってしまうと脱灰が進みます。再石灰化を優位に働かせるためには、唾液の力が十分に発揮される時間を作ってあげることが大切です。食事と食事の間に摂る間食の回数に注意しましょう。
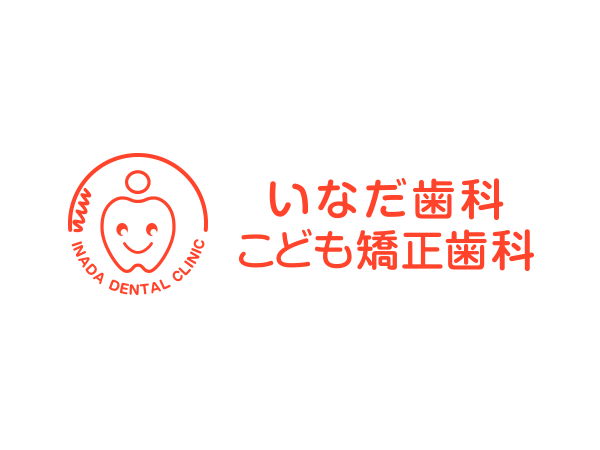
③唾液の分泌を増やす
唾液は再石灰化作用のほか、むし歯菌の出す酸を中和したり、お口の汚れを洗い流したりする働きがあります。唾液の量を増やすために食事の時にはしっかりとよく噛みましょう。唾液腺マッサージや キシリトールガムを噛むのもおすすめです。
④口の中の汚れを落とす
バイオフィルム(プラークが口腔内に長時間とどまって膜のようになったもの)に歯が覆われると、唾液をはじいてしまい、唾液のもつ再石灰化作用を邪魔してしまいます。再石灰化を促進するためには、プラークをきれいに落として唾液が十分に歯の表面に行き届くようにしておくことが大切です。
1960年代までは、「早期発見、早期治療」が行われてきましたが、今では「早期発見、早期観察管理」が推奨されています。再石灰化の力で、むし歯の初期段階であれば、自然治癒する可能性があります。
日々の生活で再石灰化を促進させて、自宅で毎日行うホームケアと、歯科医院で定期的に行うプロフェッショナルケアを受けてお口の健康を維持していきましょう☆
